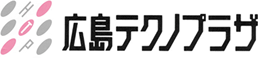ねらい
開発段階では目標達成したのに、製造段階や市場において予期しない不具合が発生し、そのつどモグラ叩き的に問題を解決しているというのが現場の悩みではないでしょうか。これは、今の開発・量産準備プロセスにおいて、量産バラつきや市場における環境条件・使用条件などに対する考慮がほとんどないためです。そこで、これらのバラつきに対する基本的考え方を身につけるとともに、対象とする現象に対して「どのような要因のバラつきがどの程度影響を与えているのか」を開発プロセス・量産準備段階で、実行可能な実験で、効率的に見つける方法論をこの研修で学ぶことができます。
プログラム 9:30~16:30 < 昼食休憩 12:00~13:00 >
|
1日目(9:30-16:30) 1.製造業における実験のあり方 2.タグチ式実験計画法の位置づけ 3.タグチ式実験計画法の手順 ②SN比の計算方法と要因効果図 ③最適条件の求め方 4.演習その1 タグチ式実験計画法を使った実験 |
2日目(9:30-16:30) 5.演習その2(穴あけ加工精度の向上) 6.タグチ式実験計画法による革新 7.タグチ式実験計画法の事例 |
3日目(9:30-16:30) 8.演習その3(よく回るコマ) ①機能系統図とは |
市場で起こりそうな故障現象を抜けなく抽出し、その原因に必要な対策を打つためにFMEA/FTAという手法があります。しかし開発・量産準備期間の短縮が必須である今、抽出できた故障原因の内の優先順位の高い故障原因のみFMEA/FTAで対策すべきです。そして優先順位の低いものについては、商品にあらかじめロバスト性を持たせておくという考え方に従ってタグチ式実験計画法が誕生しました。
◆下記の各計算が電卓またはパソコンで1分以内に出来るように、習熟して臨んで下さい。
① log{(112+122+132)/3}
② log{(1/112+1/122+1/132)/3}
③ log[{(10-11)2+(10-12)2+(10-13)2}/3]
④ 100.123
⑤ 10-0.123